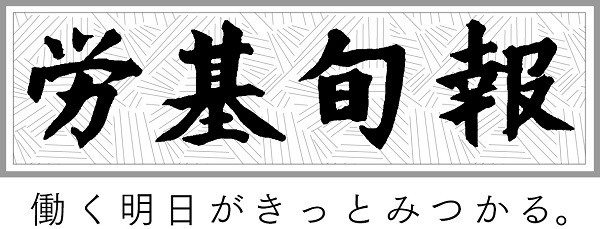■組織を発展させる内部通報窓口のつくり方⑥

アムール法律事務所講師
▶オリンパス在職中の2007年に不正疑惑を内部通報。通報を理由とした違法配転を受け提訴し、最高裁で勝訴が確定。2016年に会社と和解し21年退職。各所で講演など多数実施。
通報内容が法律上の公益通報に当たるかの判断は、窓口業務でも重要なポイントです。マスコミなど外部への通報(第3号通報)に関して解説した前回に続き、今回は社内窓口への内部通報(第1号通報)について、特に「通報対象事実」に焦点を当てて解説します。
公益通報者保護法は通報対象事実について、国民の生命・身体・財産の保護などの観点から刑事罰や行政罰(過料)が課される500の法律の違反行為と定義。内部通報の場合は、通報者が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合」その具体的行為を通報することとされています。「思料する」は「考える」などという意味で、ひっ迫性が求められるものの、実際にその行為が起きていなくても該当します。
つまり、法律違反を通報者が立証する必要はなく、第3号通報のように真実相当性も要件とされません。ただ注意すべきは違法行為の範囲で、刑事罰のない規制法や民法の公序良俗違反・不法行為、例えば傷害を除く一般的なパワハラ・セクハラなどは入らないと考えられます(消費者庁Q&A)。
果たして会社で働く普通のビジネスパーソンのどれだけが、この通報対象事実の範囲と保護要件を的確に把握した上で通報できるでしょう。法律が通報者に非常識に高いハードルを課していると言わざるを得ないのです。
私がオリンパスで行った内部通報は、裁判でコンプライアンス運用規定に該当する通報と認められましたが、法律上の公益通報とは認定されていません。度重なる配転命令に業務上の必要性がなく、通報への報復を理由とした不当な動機であることなどが認定され、訴えが認められました。しかし、そもそも初動の窓口対応が適切であれば厳しい裁判を争う必要はなく、会社にとっても建設的な改善策に繋げられたと考えています。
■専門家の判断も
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。