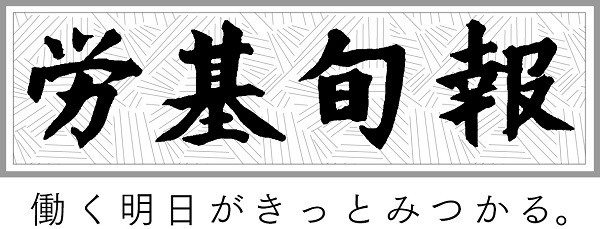■連載:人事担当者がわかる最近の労働行政
昨年1月8日に労働基準関係法制研究会の報告書が公表され、その中のかなり大きな部分を「労使コミュニケーションの在り方について」という項目が占めていました。最も議論が白熱している労働時間法制や、別途労働基準法における「労働者」に関する研究会で突っ込んだ議論が行われている労働者性の問題と並んで、この労使コミュニケーションがこれからの労働法制の在り方を左右する大きな論点であることは間違いありません。今回は、新春号向けの拡大版のトピックとして、この問題のこれまでの経緯と現在行われている議論の概要を見ていき、これからのあるべき姿を考えてみたいと思います。
■
戦後確立した日本の労働法制は、労働基準法等の労働保護法により労働条件の最低基準を設定し(個別的労働関係法)、最低基準を上回る労働条件については労働組合による団体交渉を通じた労働協約により設定する(集団的労使関係法)ことを予定しています。
しかし、こうした伝統的労働法モデルは、労働組合組織率の低下や労働者の多様化によって十分に機能しなくなってきています。とりわけ、多くの労働組合が非正規労働者に加入資格を与えていないため、非正規労働者は使用者に対して発言する機会が乏しくなっています。
世界的に見ると、集団的労使関係システムは、労働組合のみが労働者を代表しうるシングル・チャネルの国と、労働組合と常設的従業員代表機関の二本立てのデュアル・チャネルの国に分けられます。アメリカとスウェーデンは前者に該当し、ドイツ、オランダ、フランス、韓国等は後者に含まれます。イギリスは典型的なシングル・チャネルの国でしたが、EU指令の国内法化によって限られた場面でのみ労働組合以外のチャネルが設けられ、現在はシングル・チャネル・プラスと呼ばれています。
この観点で見ると、日本の集団的労使関係法制(労働組合法、労働関係調整法)は純粋なシングル・チャネルで構築されています(もっとも、アメリカのシングル・チャネルが排他的交渉代表制によって単一のシングル・チャネルを確保しているのに対し、複数組合平等主義によって組合のマルチ・チャネルが保障されています)が、個別的労働関係法における特定の場面において過半数代表に一定の役割が与えられています。
より細かく見ると、労働基準法における就業規則の作成・変更時の意見聴取や時間外・休日労働協定の締結等の当事者は、過半数労働組合またはそれがない場合は過半数代表者とされており、制定経緯から見ても過半数労働組合を原則とするシングル・チャネル・プラスとみることができます。
一方、現実の日本社会における集団的労使関係システムは、労働組合がほとんどもっぱら企業レベルで結成され、この企業別組合が労働組合法の予定する団体交渉を行うだけでなく、それよりむしろ積極的に労使協議を行ってきたことに特徴があります。
デュアル・チャネルの国では、産業別労働組合が企業を超えた産業レベルで労働条件について団体交渉を行い、従業員代表機関は企業から情報を提供されて協議を行うという分担が成り立っていますが、それが主体においても内容においても重なり合っているのです。
もっとも、シングル・チャネルのスウェーデンでも、極めて高い組織率を背景に、全国レベルから企業レベルまで労働組合が団体交渉から労使協議まで行っています。しかし、組織率が2割未満の日本では、これは多くの労働者が集団的発言チャネルから排除されていることを意味します。組合があっても非正規労働者が排除されていることが多いことは前述の通りです。
上の分類でシングル・チャネルに追加された「プラス」に当たる過半数代表者についても、常設性や機関性がなく、意見集約やモニタリングの機能を果たしうるようになっていないなど、制度上の問題点が指摘されています。また、選出手続については省令に規定があるとはいえ、実態としては会社側指名など不適切な選出方法が多く見られます。
■
従業員代表制については、既に数十年にわたって労働法学者の間でさまざまな議論が闘わされてきていますが、その意見を大きく分けると、まず、従業員代表制の立法化に積極的な意見の中にも、過半数組合があってもこれとは別に従業員代表制を設置するという併存的従業員代表制度論がある(西谷敏ら)一方、過半数組合がない事業所に限って従業員代表制を設置するという補完的従業員代表制度論があります(毛塚勝利ら)。前者が現在の労働組合の活動への低評価に基づいているのに対し、後者は実現可能性と労働組合への悪影響を懸念しているわけです。
これに対し、従業員代表制の立法化に消極的な意見の中にも、過半数組合に一定の従業員代表機能を認めるとともに公正代表義務を課すという労働組合強化論がある(道幸哲也ら)一方、労働者の選択の自由を最重視して組合強化の介入をも否定する放任論があります(大内伸哉ら)。いずれも労働組合中心主義に立ちながら、それを法的介入によっても積極的に実現すべきと考えるか、団結権を行使しない方が悪いと突き放すかで対照的となっています。
日本の労働法政策を概観すると、戦前期には内務省社会局や協調会から労働委員会法案が提起され、帝国議会に産業委員会法案が提出されたことがありますが、戦後は基本的に今日に至るまで、純粋シングル・チャネルの集団法と「プラス」に当たる過半数代表制という終戦直後に作られた仕組みを維持してきました。
1998年労基法改正により(企画業務型裁量労働制の導入という限られた場面ですが)労使委員会という常設機関が登場しましたが、労使委員会の労働側委員は過半数代表または過半数代表者が指名するため、選出等の問題点はそのままです。
この労使委員会の役割を大幅に拡大しようとする試みが、2007年労働契約法制定に向けた検討の中で行われました。2005年9月の今後の労働契約法制の在り方に関する研究会報告書は、就業規則による労働条件の不利益変更について、過半数組合または労使委員会の委員の5分の4以上の合意があれば原則として合理性が推定されるという仕組みを提起するとともに、解雇の金銭解決の要件として労働協約や労使委員会の決議を求めるなど、これを労働契約法制の中核に位置づけようとしたのです。
ところが同年10月から労働政策審議会労働条件分科会で公労使三者構成の審議が始まると、労働側はこれに猛反発しました。労使委員会の制度設計が不十分なまま同委員会に労働条件決定・変更という重要な機能を担わせることに対して労働組合が反発するのは当然ですが、労働側は過半数組合に大きな権限を与えることにも反対しており、明確な集団的労使関係モデルの構想が欠けていたようにも見えます。
この間、厚生労働省事務局からは労使委員会に代えて「事業所のすべての労働者を適正に代表する者(複数)」という提案が示されたりもしましたが、結局審議の中で消えてゆき、最終的に労働契約法10条において、不利益変更の合理性判断要素の例示として、4番目に「労働組合との交渉の状況」が並ぶだけに終わりました。
■
次にこの問題が論じられたのは、2010年代前半期に非正規労働問題の解決の道筋として集団的労使関係システムに着目する議論が提起されたときです。2011年2月の今後のパートタイム労働対策に関する研究会報告書や2012年3月の非正規雇用のビジョンに関する懇談会報告書では、「ドイツの事業所委員会やフランスの従業員代表制度を参考に、事業主、通常の労働者及びパートタイム労働者を構成員とし、パートタイム労働者の待遇等について協議することを目的とする労使委員会を設置することが適当ではないか」と、かなり踏み込んだ提案をしていました。
こうした流れを受けて、労働政策研究・研修機構(JILPT)は厚生労働省の要請を受けて、様々な雇用形態にある者を含む労働者全体の意見集約のための集団的労使関係法制に関する研究会を開催しました。
同研究会は2013年7月に報告書を公表し、①現行の過半数代表制の枠組を維持しつつ、過半数労働組合や過半数代表者の機能の強化を図る方策、②新たな従業員代表制を整備し、法定基準の解除機能等を担わせる方策、を提示しました。しかしながら、その後の非正規労働者の均等・均衡処遇政策においては、この問題意識が顧みられることはなく、2018年の働き方改革においても、派遣労働者の労使協定方式という周辺的な制度が設けられただけで、課題はそのままになっています。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。