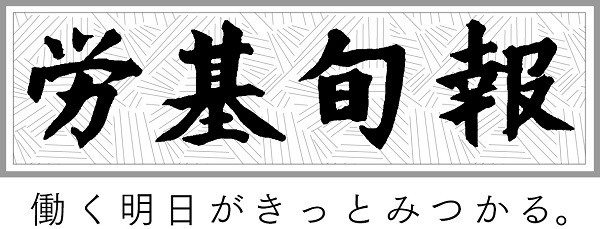■一部に限って不就労時間認める シフト減後の労働時間から計算
シフト制労働者のバックペイについての考え方として参考になる事例です。認められないとしつつ、労働者が請求した一部に限って賃金請求を認めています。自身の休職による労働時間の削減やコロナの影響を考慮して、シフトが減少した時期の平均労働時間から賃金を算出しています。
■判決のポイント
寿司店のシフト制で働く労働者は以前は週6日勤務していましたが、平成31年1月ごろからシフトの希望日が減少。同年3月にはシフトを提出しませんでした。会社は同年4月に社会保険を停止する旨を伝えましたが、原告は辞めるつもりはない、復帰する旨を述べたものの、その時期を明らかにしませんでした。 令和元年に退職証明書を交付したところ、原告は組合を通じて復帰を要求する文書を交付。原審では、合意退職の成立を否定した一方で、賃金などの請求を棄却しましたが、これを不服として労働者が控訴しました。
本判決でも退職の意思表示があったとは認めない、と一審判決と同じ判断を示しつつ、金額については、復職の時期を明らかにしていなかったなどの事情から、組合を通じて復職の交渉を行うまでは就労意思を欠いているとして、復職の交渉を行うまでの賃金請求を棄却。それ以後の一部に限って不就労時間を認めました。本人による数カ月に及ぶシフトの削減、コロナにおける休業などから、平成30年12月から平成31年3月までの平均労働時間である1カ月95時間を平均の時間として賃金を算出しています。
■判決の要旨 自らの勤務日数の減少やコロナの影響を考慮して
「控訴人は、被控訴人に対し、本件要求書を送付した同年8月9日頃まで、本件寿司店への復職時期を明確にしていなかったことが認められるところ、この間、被控訴人においては、本件寿司店の人員を補充するため、新たなアルバイト従業員を雇い入れるなどしていたのであるから、被控訴人が本件要求書の送付を受けた後、直ちに控訴人を復職させなかったとしても、被控訴人の責めに帰すべき事由により控訴人が就労することができなかったとまでは認められない」
「もっとも控訴人は、同年8月9日頃、本件労働組合を通じて、被控訴人に対し、本件要求書を送付し、本件寿司店への復職を求めたうえ、同年10月1日から令和2年1月17日まで5回にわたる団体交渉においても本件寿司店への復職を求めていたことが認められる。被控訴人においても、控訴人に本件寿司店への復職の意思があることを明確に認識しながら、同年3月、本件寿司店において、新たにアルバイト従業員2名を雇用したことからすれば、同月以降については、控訴人を本件寿司店で就労させることは可能であったと認められるから、控訴人は被控訴人の責めに帰すべき事由により就労することができなかったと認めることができる」
「控訴人は平成30年12月以降、自ら勤務日数を減少させていた上、本件寿司店は令和2年4月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業や営業時間短縮を余儀なくされ、深夜営業ができない時期が長期に及んでいる」
被控訴人の責めに帰すべき事由により就労することができなかった賃金は、「休業等の期間や深夜の営業がほとんどであったことを考慮して」「控訴人の平成30年12月から平成31年3月までの平均労働時間である1カ月95時間に時給1300円を乗じた12万3500円と認めるのが相当である」
■解説
退職の成否がどう判断され、請求が可能な賃金がどう算出されているのか。
シフト勤務の労働者がシフトを入れず、休業が多くなったのであれば、辞めるのではないかと会社は判断しがちです。シフトを入れなくても社会保険や雇用保険の保険料を負担しなくてはならないので、退職させたいと考えがちです。
退職の合意が成立しないことについて、「何ら書面が作成されていないこと」「退職の意思の確認を明確に行っていないこと」「退職時期が判然としない上、最終勤務日の勤務以降も店舗の鍵を所持し、店舗に私物を置いたままにしている」ことが問題として指摘されています。
そこで実務では、退職合意を成立させたいと考えるのなら、労働者から退職意思表示の書面を提出もらうこと、退職の意思表示を確認することが必要となります。
なお、休業期間のバックペイを認めつつ、シフトが減少した期間の労働時間から賃金を計算しており、一部の賃金請求に限って認めています。
シフト削減は不利益大 決定権限の乱用に当たる
■シルバーハート事件(東京地裁令和2・11・25判決)
シフトを削減されたとして、社会福祉施設の従業員が未払賃金を求めたが、雇用契約書に勤務日数の記載はなく、「シフトによる」としていたが、労働者は、勤務日は「週3日」とする旨の合意があったと主張した。
判決は、合理的な理由なく日数を大幅に削減した場合、シフト決定権限の濫用に当たると判断。直近3カ月の賃金額との差額支払いを命じた。
従前の勤務実態によると、必ずしも週3日のシフト勤務が組まれていたわけではないこと、介護事業所において本件労働者が従事できる役割は限定的であるため、勤務日数を固定することが困難であることを指摘し、労働者の主張を認めなかった。
一方、シフト制勤務の労働者にとって、シフトの大幅な削減は収入減に直結し、その不利益が著しいとして、民法536条2項に基づき、不合理に削減されたシフト分の賃金請求権を行使できるとした。
勤務実績を基に、少なくとも、1日しかシフトに入れていない月と一切シフトに入れていない月は、シフト決定権限の濫用に当たるものと判断。 直近3カ月の賃金の平均額から算出した金額を認容した。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。