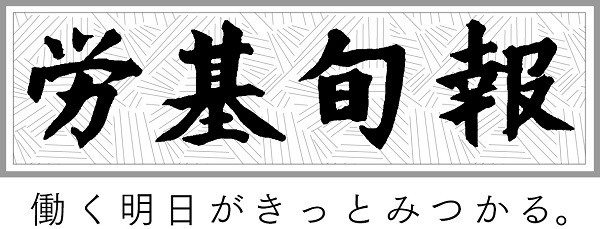■新・働く人の心と体の心理学 第51回 著者:深沢孝之
最近、ある地方公共団体から、発達障害の特性のある部下への接し方について研修をしてほしいという依頼がありました。主に管理職を対象にした研修会で、実際現場では発達障害と診断された人や、それが疑われる職員とのコミュニケーションに苦慮しているケースが増えているとのことでした。それまでの無闇に叱ったり、できないところばかりを注意するようなやり方は下手をするとトラブルになったり、ハラスメント認定されてしまうかもしれず、管理職が自らのコミュニケーションを省みて、改善を目指すのはよいことです。その時に発達障害という概念を頭に入れておくことは、相手を理解しようとする態度を養うこ
とになり、それもよいことです。
それで私は研修を引き受けましたが、いざ内容を組み立てるときに困ってしまいました。接し方といわれても実際、万人に通じるような方法なんてあるわけないからです。確かに発達障害にはいくつかの名前、診断名があります。自閉症スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などです。それぞれには特有の特徴があり、ASDと診断される人たちには、コミュニケーションが苦手とか、こだわりが強いとか、確かに共通しているところはあります。だからこそ同じ診断がつくわけですが、しかし、その在り方は実に千差万別です。また中には、各発達障害のいくつかの特徴が診断名を超えて重なっていることも少なくありません。それに一人ひとり違う人生があり、そこから形成された性格も違い、仕事も職場も違うのだから、それぞれの問題や悩みはとてつもなく多様です。それに応じてニーズが違うのですから、私自身、同じ診断名でも、ある人にした助言と全く正反対の助言を別の人にすることもよくあります。
さらに事態をややこしくしているのは、発達障害が知られるにつれ、医療機関の過剰診断が見受けられることです。コミュニケーションが苦手で、知能検査の結果、知的能力にアンバランスさが認められれば、即ASDと診断されてしまうようなことはよく聞きます。その結果、発達障害が増えているような印象を与えているのではないか、とする意見もあります。
実は発達障害と似た症状を示すけれど、実は違う診断をつけた方が適切なケースもあります。虐待やトラウマを背景にした愛着障害などです。こうなると誤診です。しかし医師にしてみれば、限られた診療時間と回数で、正しい診断を下すのはけっこう難しいものです。結局、人を理解するには、信頼関係を築きながらある程度の時間をかけなくてはできないのですが、現実の医療体制では限界もあります。
受ける側は、発達障害と診断されたからといって、決定的なものではなく、暫定的なものであり、状況によって変わり得るということを理解しておく必要があるでしょう。
■グレーゾーンを理解する
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。